プレーパークは子供と防災の意識を高める絶好の遊び場!
 教育
教育
2018.02.08
娘がまだ生まれていない頃から、時折息子を連れて通ったプレーパーク。(プレーパークというのは、冒険遊び場という名称でも知られています。)
最近では1~2か月に一度は必ずプレーパークで遊ばせるようにしています。
プレーパークは森のようちえんの活動拠点としても使われていて全国に広がりを見せていますが、一体プレーパークってどういうところなのか、また私の中で、どう防災の意識が高まっていったのか、体験を交えながら紹介したいと思います!
※私が防災を常に意識する理由は次の記事に書いていますので、ご参考までに。(【防災グッズ】おすすめは?子供とお出かけ時の必須アイテム:参照)
- 遊びながら楽しく防災トレーニング
- どんな風に防災に役立っているのか?
- プレーパークってどんな場所?
遊びながら楽しく防災トレーニング
ちょうど2年前に「災害時に役立つサバイバル術を楽しく学ぶ 防災ピクニックが子供を守る」という書籍を読みました。
ママプラグ KADOKAWA/メディアファクトリー 2014-02-21
小さなお子様のいらっしゃるママさんにはおススメの書籍です。
読んだ後、たくさん考えさせられました。そして防災ピクニックを友達家族とやってみたいと思いましたが、なかなか実現できないままでいました。
「そのかわり防災キャンプをしようよ!」という声があがり、年に数回キャンプ広場で開催してみました。
我が家は家族一人ずつ、防災バッグと寝袋を持っています。
でも被災した時に初めて使う、、、というのではまずいですし、足りないものがあるといけないので、子供が小さいうちは年に一回、中身の再点検も兼ねて、庭で防災グッズを使って調理をし食事をする、という活動もしてきました。
でもですね、やってみた感想としては、庭もキャンプ場もどちらもお膳立てがあるのです。
万が一足りなければ、家に戻って補充したり、キャンプ場では設置されているものや、準備されているものを使い、足りなければ友達から借りて、ないものはスーパーへ買い出しに行く、みたいな。
ところが、プレーパークの場合、ドラム缶や鍋はありますが、それ以外は全部自分で準備しなくてはいけません。
まず自分たちで木を運んでくるところから始まり、火も自分たちで起こします。
キャンプだと人数も多く大がかりなので、子供主体でやると、物事の進み方が遅くなってしまいますし、時間の拘束もあり、どうしても大人主体で運営してしまいがち。
しかし、そもそもプレーパークは子供が主体になって遊ぶ場所。
ここではマッチをこするところから、どうやればうまく火がつくのかも、プレーリーダーさんが指導してくれます。そこで子供は火の扱い方や危険な一面も学んでいきます。
マッチで火をつけることは問題ない息子も、いざドラム缶の中に手をいれて、うまく火がつかなかったり、指に火がつきそうで熱いと思うと、少し腰が引き始めていました。
でもプレーリーダーさんが後ろから「火はお友達なんだよ、怖くないからね。大丈夫だよ~。」と声をかけてくれたり、アドバイスをしてくれたりして、何度目かにようやく着火出来、笑顔が浮かびました。

もちろん、どこでも勝手に使っていいものではないということや、子供一人では絶対火をつけてはいけないということは、しっかり教える責任がありますし、それが出来る人格と精神年齢に達しているかも、親が判断する必要があります。
今は焚火も出来ないご時世なので当然ですが、娘は煙の避け方もよくわかってなくて(キャンプでは出来上がり品を、煙のないところで食べさせていたことに後で気づく母。)、そういうことも一つ一つ教えていく機会になっています。
お腹を空かせた娘のために、焼いたポテトをお皿に乗せたものの、私も娘も熱すぎて持つことができず、冷ますために割りたいのだけど、プレーパークには包丁がないということをそこで知りました。(あたりまえだけど。)
そこで、いつも常備している救急ポーチの登場です!
マルチツールはしょっちゅう活躍していますが、その中の小さなナイフ(刃渡り3.5cm)を使う機会はなかったので、ついに使う時がやってきました!しっかり切れて役立ちました。

※このナイフは刃渡り6センチ以下のものですが、刃物の所持は自己責任でお願いします。
VICTORINOX(ビクトリノックス) 2012-03-08
今は調理用に、小型のセラミックナイフを持参するようにしています。
こんな風に実践してみて、初めて気づくことの多さに愕然としたのです。
どんな風に防災に役立っているのか?
最初は自然遊びを体験させてあげたいという気持ちで連れていっていたのですが、子供たちも大きくなり滞在時間が長くなって、おいもを焼くくらいでは足りなくなり、そこで調理して初めて「これは防災に役立つな」、と思うようになったんです。
お弁当持参もできますが、うちは防災も兼ねて、敢えて食材を調達して、そこで調理するようにしています。
プレーパーク側にそういう目的はありませんし、子供もそこを意識していませんが、遊びの中で自然とトレーニングされている部分もあり、私にとっては、防災用の持ち物を見直す機会になっています。
私たち親子は化学調味料や添加物に弱いので、なんでも食べることができません。
それでも非常時の場合は目をつぶるしかないものもあるよね、と防災用に野菜のたくさん入ったインスタント味噌汁と、5年保存のきく具だくさんの非常用ごはんを貯蔵していたものを、キャンプの時に朝ごはんとして試しに作って食べてみたら、両方ともアミノ酸が入っているため、2倍の濃さで舌を刺激してきてビックリ!!
私は食後、気分が悪くなってテントで横になる羽目に・・・、という経験があります。
準備していても、ダメなものもあるんだな~」と思い知りました。
被災時に親が不調では、守れるものも守れません。
ある時は、プレーパークで昼前に帰るつもりが、子供たちがもっと遊びたいというので、仕方なくコンビニで小さいカップラーメンを買って調理して食べさせたら、翌日二人とも発疹が出てました・・・。
これが被災時だったら・・・。子供が具合悪くなったら、もっと最悪です。
配給されるものにも注意しないといけないな、と思いました。
それで、今では自然食品の袋ラーメンを何種類か買ってテイスティングしてから、一番好評だったものを常備しています。
家族の中でも、この人は醤油味、この人は味噌味、この人は塩味が好きだからと用意したら、鍋が一つしかない時に、最後にいちいち分けてから調味料を一つずつ入れなくてはならない不便さがある、ということもプレーパークで作った時に気がつきました。

今は、みんな醤油味に揃えています。
最近は、スーパーでも、化学調味料無添加のインスタント味噌汁が出てきたので、とっても嬉しいです!
野菜を切るまな板も、キャンプ場にはあったので、全然気にしてませんでしたが、プレーパークにはありません。全員分携帯まな板を揃えるのは大変だし、荷物もかさばるので、牛乳パックを携帯まな板替わりにして、一人ずつバッグに入れるようにしました。
そして、子供たちが遊ぶのをじっと待っている親としては、カイロだけではなかなか足元が温まらず、しょうがスライス(生姜で冷え対策!ダイエットやがん予防に効果的なレシピは?:参照)を持参するようにして冷え対策をしたり、自然の中で工夫していくようになりました。
また、プレーパークに持っていくためのグッズは巾着袋に入れておき、防災バッグの中から簡単に取り出せるようにしました。
キャンプはしょっちゅう出来ませんが、プレーパークには時間があれば簡単にいくことが出来るので、とても助かっています。
[ad#co-1]
プレーパークってどんな場所?
ところで、プレーパークはどのような場所かご存知ない方のために少し紹介したいと思います。
プレーパークとは、「自分の責任で自由に遊ぶことを基本に、身近な素材を使っていろいろなことができる遊び場」です。
出典:www.city.musashino.lg.jp
プレーパークは東京が圧倒的に多いのですが、全国各地にあり、現在は205か所で開催されています。
日本冒険遊び場づくり協会 – 遊び あふれる まちへ!
東京は自然遊びできる場所が少ない分、そういう場を設けてあげたい、と発足してくださる方々が多いのだと思います。
そもそも東京のある夫婦のある思いから広がっている運動なので、東京が集中しているのは当たり前なのですが、その思いは着実に全国各地へと広まっています。
森のようちえんも日本の冒険遊び場が生まれたのは、当時世田谷区経堂に住んでいた大村虔一・璋子夫婦の「わが子の遊び環境は自分たちの子ども時代とは違っている。わが子にもあの遊びの世界を体験をさせてあげたい」という想いからでした。
出典:http://bouken-asobiba.org/
私自身も遊び場といえば公園でしたが、時には裏山で遊ぶことも多く、自然の中ですくすく育ったほうだと思います。
帰省した時に、子供たちを連れてその裏山に行ってみようとしましたが、現在ではどこの箇所からも立ち入り禁止となっており、がっかりしました。
子供には厳しい時代だなあと私でも感じているところです。
今の時代では、不審者とか何が起きるかわからないという気持ちがわいて、私でさえも自分の子供たちだけで山遊びとか行かせる勇気はないです・・・。自分が過ごした子供時代がいかに平和だったかを痛感しています。
だからこそ、このプレーパークはとってもありがたい存在なのです。
私は今まで5か所のプレーパークに参加したことがありますが、集まる子たちも雰囲気もそれぞれ特徴があって、どこも同じようで違うところが面白いと思います。
どこにいっても、子供たちはやっぱりハイジブランコが大好き!設置してくださるリーダーさんたちに感謝です。

現在は、自分の住んでいる市の開催地より隣りの市の開催場所のほうが近いので、そちらに参加しています。
まとめ
プレーパーク常連組の男の子たちは、なんでもないことのように上手に火を扱い、調理することが出来ています。いろんなことをよく知っていて、そういう姿を見ると感心してしまいます。
多くの森のようちえんの子供たちは、一年中野外で活動しています。彼らの園生活の様子を見ていると、震災時になってもストレスなく、たくましく生活できるのは、間違いなくこういう子たちなんだろうなって思います。
ただプレーパークでもサバイバル術としては完全ではありません。家でしかできないことも備えていく必要があるなと思っています。(例えばトイレ問題。)
東日本大震災も、熊本の地震も寒い季節でした。これが真夏に起きたらどうだろう??と、考えただけでゾッとします。
それでもこの地震大国で生きていく以上、防災は避けて通れない問題です。かといって、眉間にしわを寄せて子供たちに訓練させるというのもなんですし、プレーパークのような遊びの中で、自然に生き抜く力を身につけていってくれたらな、と願っています。










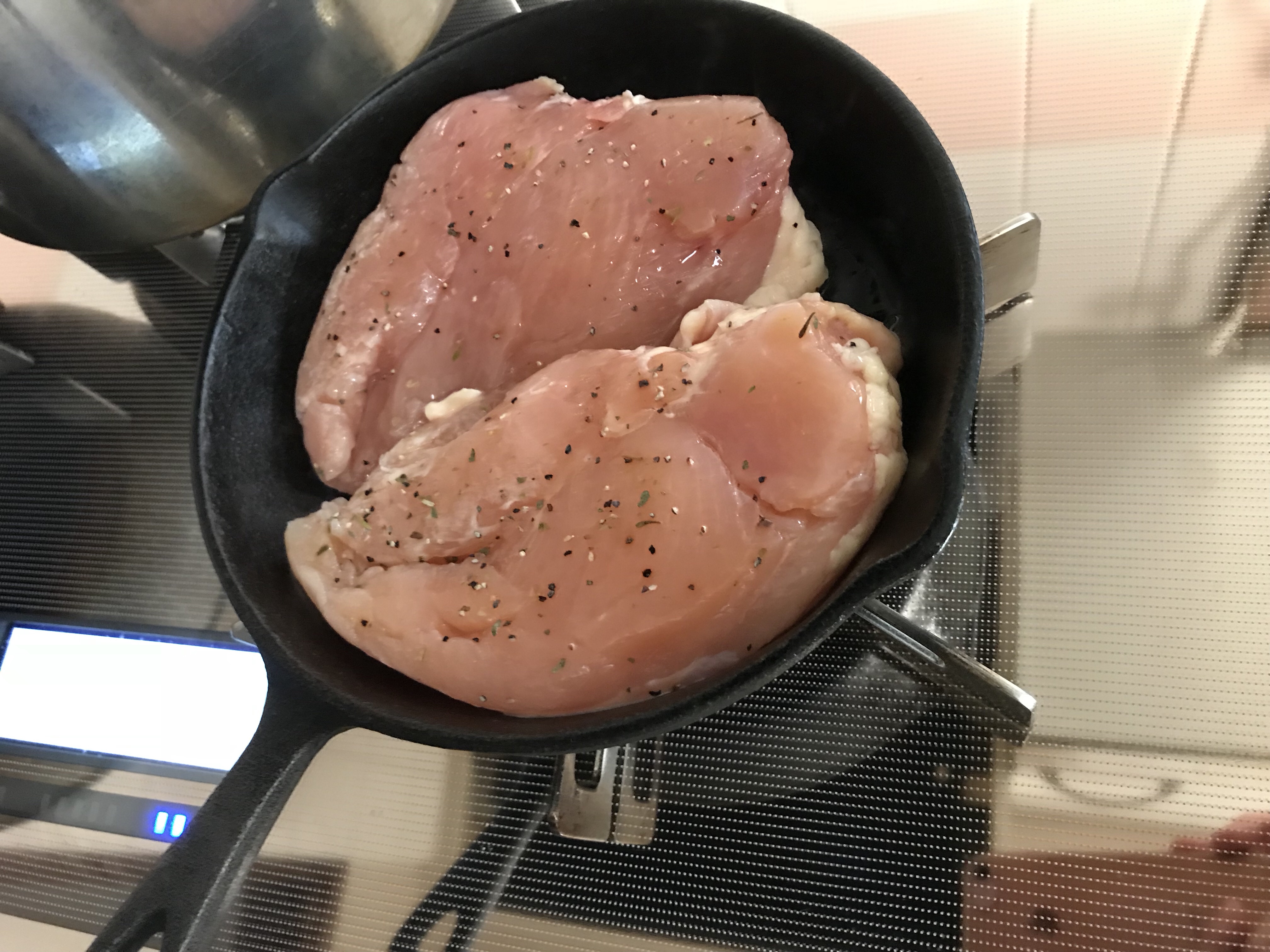
コメント